一番つらい時期➡【3月、4月】学年の変わり目で、陥りやすい罠!
3月になり、通塾中の方々も新学年のカリキュラムに入って、数週間が経過した頃かと思います。
J太郎の経験から言わせていただくと、
この【学年の切り替わり】の2月~4月が親子共々、一番辛かったんです!
4年➡5年
5年➡6年
のいずれの時期も、非常にキツかった!
![]()
この時期は、
各塾の合格実績なども出そろって、親としても少し浮足立つ時期でもあります。
そして、その実績を見て、「うちの子も、ここ位はイケるか!!?」などど、考えたりします。
一方、子供にとっては、通塾日が変わり、(増えて)
今までのルーティーンが大きく変わる時期となります!
ルーティーン、習慣の変化に対応できない‼
前の学年では、上手く回っていた1週間のスケジュールが、
学年が変わった途端に、大きく変わらざる得ない、そしてまわらなくなるんです。

ここで、【親子でのバトル】【子供の焦り】【復習がまわらない】
というのが、必ず起こりました。
![]() 我が家では、大まかなスケジュールは私(父親)が立てて、
我が家では、大まかなスケジュールは私(父親)が立てて、
【月曜日は、算数の間違えた問題【難易度3以外】、漢字道場1回目、理科グノラー】
【火曜日は、計算マスター、その日の確認テスト前の復習➡通塾】
などと大まかに決めて置き、さらに、その中でも優先度を3~1 で付けておきました。
そして、J太郎には、「優先度3は必ず、それ以降は自分の判断でできるところまで、」
というような形で指示。
これは、中学受験通じてやっていました。
学年の変わり目、これが一変します。
学年の変り目は、親の出番‼
「どの部分が本当に重要か」
「どの部分にどれだけ時間がかかるのか」
「捨てていい部分はどこか」
「何回まわせば、定着するのか」
などを、親が認識するまでに、1か月以上はかかりました。
その間、J太郎は、
時にはオーバーワークとなりパニック状態、
時には定着度が低く確認テストで大失敗。
相当メンタルをやられていたと思います。

そして
「ちょっともう追いつけないかも…」「グノーブルのカリキュラム、自分には無理かも…」
という心理状態になっていました。
今、そんな方もいらっしゃいませんか?
でも!大丈夫です!
はっきり言って、慣れます(笑)
そして、その為には、親主導できちんとコントロールする事が大事です。
宿題、家庭学習、復習、をどうやって取捨選択していくのか。
これは、子供には判断できません。
まじめな子ほど、パンクします。
だから、親がきちんと間引いて
「とりあえず、ここまでやればいい」
というゴールを子供に提示してあげると、
心理的負担もグッと減ります。
もちろん、これを行うためには、
親がグノーブルのテキスト量や
重要度を把握する事が必要です。
(仕事などで大変だと思いますが、学年始めは特に、介入していった方がいいです)
![]()
親が量をコントロールしてあげて!
例えば、前の学年で、3回復習していたから、
その習慣のまま続けようとすると、パンクします。
大丈夫、グノーブルの通常授業、土特、日特、何度も同じ例題が出てきます。
間引いて大丈夫です。
是非、新しいペースをつかませてあげてください。
授業で何度も復習が出てきますから。
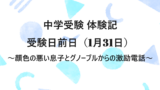
とにかく通常授業の基本レベル・標準レベルをがっちりとやって、
無理に難しい問題には時間を割かないようにして、コントロールしてあげてください!
我が家では、
GW前あたりには新学年のペースがつかめてきて、
親子バトルや、子供のパンク状態も一気に減りました!
あと、補足ですが、
親の大事な役割の一つに、【テキスト整理】がありますね。
学年が変わると、テキストも増えて、家の中が(机の上が)悲惨な状態になりますから!
ここも、こども任せはせずに、親が整理していました。
J太郎にやらせると、おそらくテキスト整理だけで、夜中になります(笑)
受験を終えて気づきましたが、復習回が沢山あるので、
あまり以前のテキストを引っ張り出して、何かをするという事はなかったのですが、
そこも、親の腕のみせどころ!
ご参考までに!
![]()
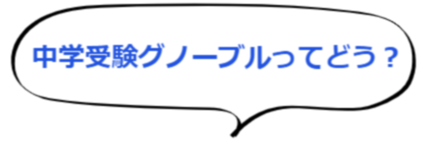
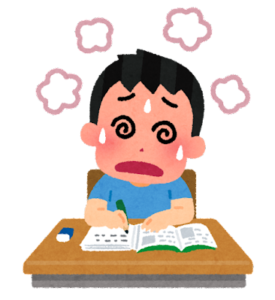


コメント